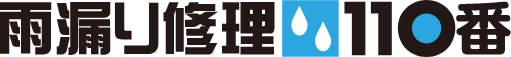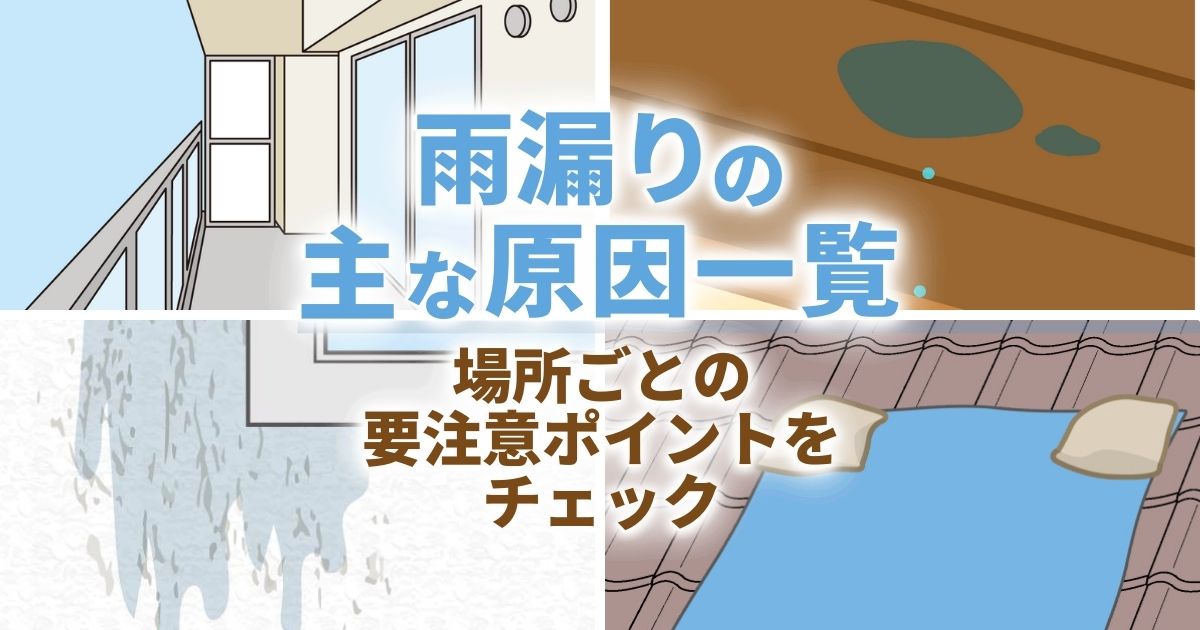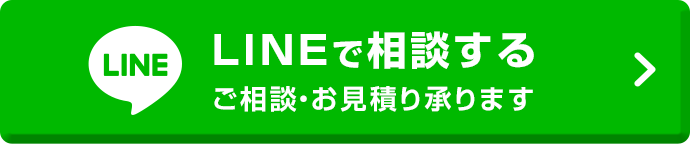屋根は形も素材もさまざまです。
雨漏りへの影響を考える前に、屋根の形や素材の違い、メリット・デメリットをおさえます。
日本でよく使われている屋根材も取り上げ、最終的に「雨漏りしやすい屋根・しにくい屋根」を分けてご紹介します。
形と素材に分けられる屋根の種類

屋根の種類は豊富です。形が違うだけでなく、使われている素材もいくつかあります。そこで、形と素材の2つに大きく分けて、屋根の種類を見ていきます。
| 屋根の形 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 切妻屋根 | 日本で一番多く使われている三角屋根。 屋根の頭頂である大棟から、下方に伸びている形状をしているのが特徴 |
構造が単純なのでコストを抑えられる 換気のしやすい構造にできる |
壁面に雨水が当たりやすくなるので、壁から雨漏りする危険が高い |
| 片流れ屋根 | 一面だけで構成されているシンプルな構造。 デザイン性が高いことから近年人気が上がっている屋根 |
初期費用を抑えられる 太陽光パネルの設置面積を広くとれる |
雨水や日光が当たりやすいため外壁が劣化しやすく、壁面からの雨漏りに繋がることがある |
| 寄棟(方形)屋根 | 一般的によく見られる屋根。 大棟があるのが寄棟、ないものを方形と言う。 屋根は4つの面で構成されている |
雨や雪を分散してくれる 重い屋根の場合、風の耐久性が高くなるので台風に強いと言われている |
初期費用のコストが高め 雨樋や棟が長い、やや複雑な構造のため雨漏りリスクが高い |
| 陸屋根 | 屋上があるタイプの水平な屋根。 アパート・マンションでよく見られるが、最近では一般住宅にも普及している |
屋上スペースを活用できる。 メンテナンス時に足場が安定しているので安心 |
屋根に傾斜がない 壁に直接雨が当たる、という理由から雨漏りしやすい |
| 入母屋屋根 | 切妻屋根と寄棟屋根の特徴を併せ持っている構造が複雑な屋根。 瓦を使用している屋根に多く見られる |
屋根裏の通気性が高い 寄棟屋根と同じく4面の構成なので、風に強い |
構造が複雑なので、雨漏りリスクがあり、メンテナンス時などで施工費用が高くなることがある |
| 招き屋根 | 屋根面が段違いになっているのが特徴。 差しかけ屋根とも呼ばれている |
初期費用が安め。風に強く、屋根裏の通気性や断熱性が良い | 雨仕舞いを疎かにすると、雨漏り被害に遭うことがある |
| はかま腰屋根 | 建築基準法による制限がある場合に取り入れることがあります。 切妻屋根の妻側を一部切り取った袴のような形が特徴 |
建築基準法などに引っかかるリスクを回避できる | 切妻屋根と比べると屋根の形がやや複雑化するため、雨漏りの発生が心配になる |
| 越屋根 | 屋根の上に小さな屋根を設けた構造をしているのが特徴 | 屋根部分に、窓を取り入れることによって採光や風通しのために役立つ | 屋根構造が複雑なためメンテナンス時にかかるコスト、雨漏りの多発が懸念される |
※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。
屋根の素材の特徴とメリット・デメリット
| 屋根の形 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| セメント瓦 | 見た目は日本瓦に似ている。 厚型スレート、コンクリート瓦とも言われる |
日本瓦と比べて価格は安い 耐久性があり、塗装ができる |
割れやすい 雨水の侵入や劣化を防ぐために塗装のメンテナンスが必要 |
| 石粒付ガルバニウム | ガルバニウム銅板の欠点を補った屋根材。 近年、需要が高まっている |
金属のため割れない 基本的にメンテナンスが要らない |
まだ新しい素材のため、コストがかかることがある |
| トタン | 工場や倉庫でよく見る、亜鉛をめっきした鋼板。 ほかの屋根材と比べると軽い |
価格が安い 耐震性に優れている |
雨音がする 錆びやすいので、雨漏り防止のためにも定期的なメンテナンスが必要 |
現代で広く使われているスレート屋根

よく見かける屋根材であるスレート屋根は、さらに細かく種類が分かれます。スレート屋根の特徴と、原因・対処を確認していきます。
スレート屋根の種類と特徴
スレート屋根での雨漏り原因と対処
※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。
昔からよく使われている瓦屋根

スレート屋根と同様、瓦屋根もよく見かける屋根材のひとつです。瓦屋根のなかでもさらに分かれる種類と特徴と、主な原因と対処を取り上げます。
瓦屋根の種類と特徴
日本瓦全体の特徴としては、耐久性がある、断熱性があるというメリットをもつ反面、重量がある、瓦自体が高価というデメリットがあります。
瓦屋根での雨漏り原因と対処
※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。
雨漏りの大きな原因になる屋根

屋根からの雨漏りは、天候などの自然現象による経年劣化などが関わっているので、避けられない部分もあります。少しでも長く屋根を使っていくために、屋根の種類を選ぶ際は、雨漏りしやすい屋根・しにくい屋根を参考にしてみましょう。
屋根からの雨漏り原因
屋根の種類によって、スレートの浮き、瓦のズレなど、多少原因は異なりますが、それらの原因を作っているものは同じと言えます。
- 強い風や豪雨
- 地震
いつも外にさらされている屋根は、雨や風や地震などの自然現象に大きく影響を受けています。
劣化するのは当たり前と考えて、どのような屋根を選んだとしても定期的に状態を見てあげることが大切です。
雨漏りしやすい屋根
■陸屋根
勾配がなく、屋根に水が溜まりやすい構造のためおすすめできません。建物をおしゃれな外観にしたいということで、どうしても外せないというときは、高性能な防水層を選ぶようにします。
■陸屋根
雨漏りの危険が高い屋根です。もし、雨漏り修理が必要になっても構造がとても複雑になるので、原因究明に時間がかかるとともにコストもかかってしまうことが多いです。
雨漏りしにくい屋根
以下は雨漏りしにくい屋根ですが、注意点があるので確認していきましょう。
■切妻屋根
屋根はシンプルなものが一番といいます。この屋根は構造がシンプルなので、屋根に強いこだわりがなければ何かと安心して使える屋根です。しかし、妻側の壁面には直接雨が当たるので、壁からの雨漏りには注意が必要です。
■片流れ屋根
雨仕舞がし易い、構造が単純なので雨漏りしにくい屋根と言われています。しかし、軒と反対側の面の壁に雨が当たりやすい、屋根に当たる雨の負担が一面に集中し、樋から雨水が溢れてしまうトラブルもあります。
■寄棟・方形屋根
屋根の構造から、壁に当たる雨を防ぐことができます。ただ、山や谷が多い構造のため雨仕舞いが難しい、軒の結合部分が劣化すると雨漏りになることもあります。
■入母屋屋根
樋から雨水が溢れてしまうことは少ないですが、結合部分が多いため劣化すると雨漏りになることがあります。避けるためには、定期的なメンテナンスが必要ですが、構造の複雑さゆえに業者による工事費用が高くなる傾向にあります。
■招き屋根
屋根が段違いになっているので、雨漏りリスクはないとはいい切れませんが、雨仕舞いはしっかりと行うとともに、定期的な点検をしていれば防げると言われています。
たとえ雨漏りしにくい屋根でも、大規模な雨漏り修理や、高所でシーリング材を使うなどの危険な応急処置になることを避けるためにも、屋根や壁などの定期的なメンテナンスが必要と言えます。
まとめ
屋根の種類による雨漏りへの影響のポイントは
- 屋根は大きく形と素材に分けられる
- 形や素材、その組み合わせを考えると種類は豊富
- よく使われているスレート屋根と瓦の種類は、さらに細かく分類されている
- 屋根からの雨漏りリスクを少しでも下げるために、メリット・デメリットを踏まえた屋根の種類選びは大切
- 雨漏りしにくい屋根を選んだとしても、定期的なメンテナンスは必要
屋根の種類に迷ったら、設置を予定している地域の天候や、屋根に必須のメンテナンスにかかる費用も考慮して、雨漏りしにくい屋根のなかから選んでみましょう。