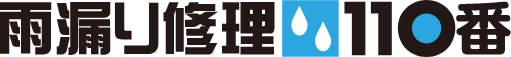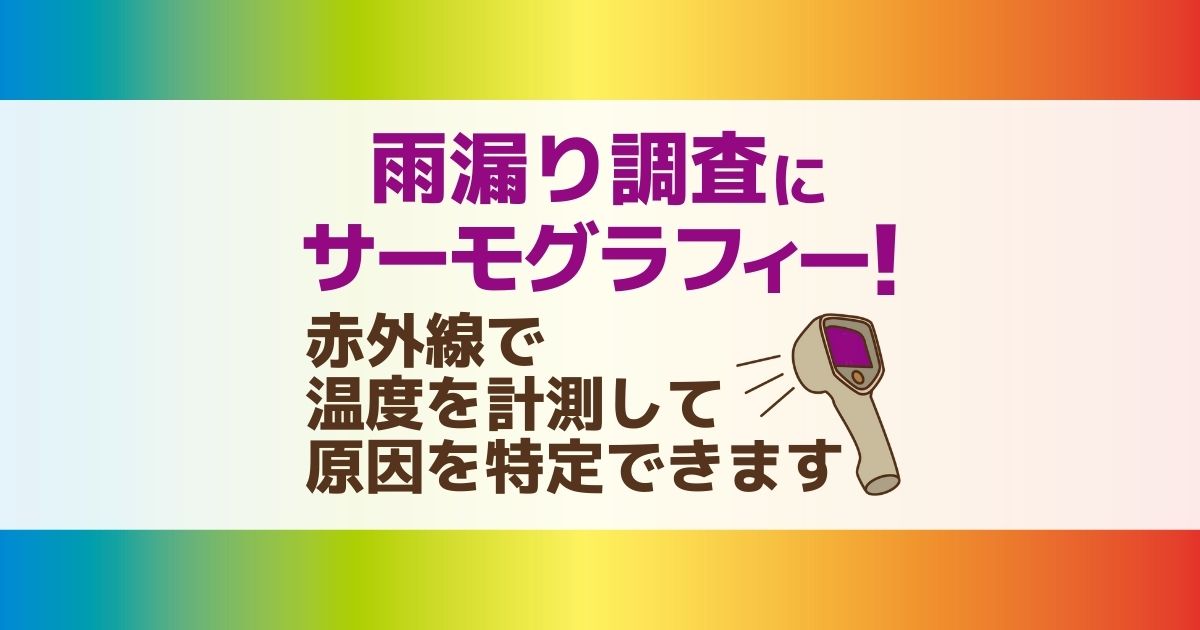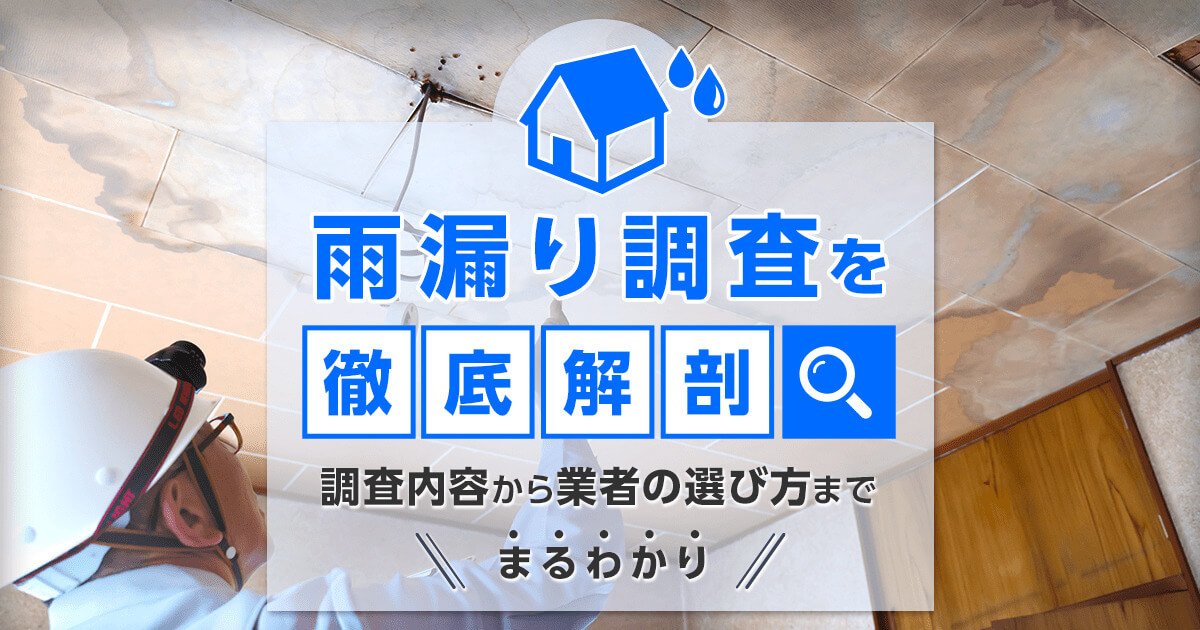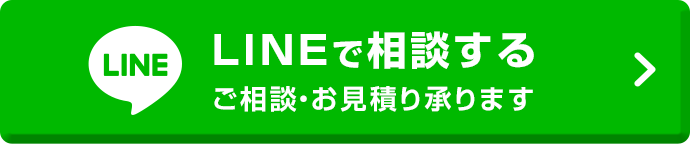雨漏り調査と聞くと、目視や散水試験をイメージされるのではないでしょうか?
しかし、近年では赤外線サーモグラフィーを使用した方法が注目を浴びています。
赤外線を使用する一番のメリットは、その正確性です。
今回は、雨漏りにおける赤外線サーモグラフィー調査についてご紹介します。
原因箇所を正確に突き止めることのできるその仕組みとはいったい何なのでしょう?
調査をおこなう建物にも向き、不向きがあるので、そのような注意点についてもご説明していきます。
雨漏りでお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
赤外線サーモグラフィー調査の仕組み
赤外線サーモグラフィー調査とは、高感度赤外線カメラを使用して雨漏りの原因を突き止める方法です。
怪しい箇所をカメラで撮影し、検査をおこないます。
カメラを使用することで赤外線反射のエネルギーを検出できるため、その温度分布画像の色の違いで雨漏り部分を正確に突き止めることができるのです。

雨漏りが起きている箇所は、雨水の影響で温度が低下しています。
このような細かな違いこそが赤外線調査では重要です。
水分があるか、ないかの温度差は1℃ほどしか違いがないため、自分で判断することは極めて困難です。
しかし、サーモグラフィーカメラを使用することで、しっかりと色分けがされるため、正確に判断することが可能になります。
その発見率は99%以上とまで言われているため、とても確実性の高い方法なのです。
※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。
調査に向いている建物と向いていない建物の違い
雨漏りの発見に赤外線サーモグラフィーを使用するというのはとても効果的な方法になります。
「せっかくなら精度の高い調査を依頼したい」とお考えになる方もいらっしゃることでしょう。
しかし、赤外線サーモグラフィーはどの建物でも使用することができるという訳ではありません。
- 建物が全面道路に面している
- 建物の立地場所が角地
- 調査対象箇所と隣地の距離が5m以上離れている
- 雨漏りがサッシや壁際から起きている
- 屋根がトタンやガルバリウムなどの金属製
- 調査対象箇所と隣地の距離が4m未満
- 周囲の建物に囲まれてしまっている
- 周囲の電線や木々に囲まれている建物
サーモグラフィ調査で雨漏り以外にわかること
雨漏りの原因は赤外線サーモグラフィーを使用すれば突き止められます。
これだけでも十分役割を果たしますが、なんと結露など他の欠陥を発見することもできるのです。
なぜそのようなことまでできるのか、その理由をご紹介します。
結露の発生
赤外線サーモグラフィーには、断熱アラームと呼ばれる機能が備わっています。
断熱アラームを使用することで、設定温度より高い、もしくは低い場所を他の色で表示できます。
例えば設定温度を17℃にしていた場合、その温度を下回るようであれば緑色など異なる色で表示されます。
温度の低い箇所は結露を起こしている可能性があるので要注意です。
壁の裏側の状態を知ることができるため、異変にいち早く気付けます。
温度差以外にも、温度が低い部分の形を知ることができるため、そこから色々な問題を判断できるのです。
断熱材の欠損
水の問題だけでなく、断熱材の欠損具合を知ることもできます。
断熱材に不具合が発生している場合は、冷暖房を使用した際のエネルギーロスが大きくなるといった異常が発生するのです。
このような違いも赤外線サーモグラフィーだからこそ知ることのできるポイントです。
対処すべき箇所を特定することができるため、簡単に対策を施すことができます。
少しでも怪しいと感じる箇所があれば、重点的にチェックするとよいでしょう。
すべての欠陥を発見することはできませんが、目視では確認できない細かな異変を判断することは可能です。
赤外線を使用するため、建物を壊す必要もありません。
物件を購入する前でも、比較的簡単に欠陥の有無を確認することができるでしょう。
このようなメリットもあるため、気になる方はお試ししてみてもよいかもしれません。
※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。
雨漏り調査はプロにおまかせしましょう!
赤外線を使用する場合でも、プロにおまかせすることをおすすめします。
赤外線サーモグラフィー調査では、色の違いだけでなく、建物の構造、外部・内部の温度環境、材料特性などの要素から総合的に判断したうえで、熱画像と照らし合わせていきます。
温度差の原因が雨水によるものかの診断など、複雑な作業を伴うのです。
建物の撮影も天候や日射量、撮影面の方位などに気を遣っておこなう必要があります。
正確に診断するためには、環境面にも注意しなくてはいけません。
水分以外にも、壁面の汚れや地面の照り返しによって温度差が生じるため、この見極めをする技術も必要になります。
もちろんサーモグラフィーの撮影技術必要ですが、建築知識がさらに必要になるのです。
プロによっても個人差が出るので、経験豊富なプロへと診断を依頼しましょう。
「赤外線建物診断技能士」という資格もあるので、これを保持している方におまかせすると安心です。
雨漏り調査方法はこちらの記事にまとめてあるので、ぜひご覧ください。
まとめ
今回は雨漏りの原因を赤外線サーモグラフィー調査で突き止める方法をご紹介してきました。
原因箇所の特定はとても難しい作業ではありますが、サーモグラフィーを使用することで正確性の高い判断を下すことが可能です。
雨漏り以外にも結露などの欠陥を発見することもできます。
しかし、調査を実施する建物にも向き、不向きがあるので注意してください。
複雑な作業と豊富な知識が必要になるので、調査はプロにまかせましょう。
雨漏りの原因がわからずお困りの方は、一度業者による調査を試しみましょう。